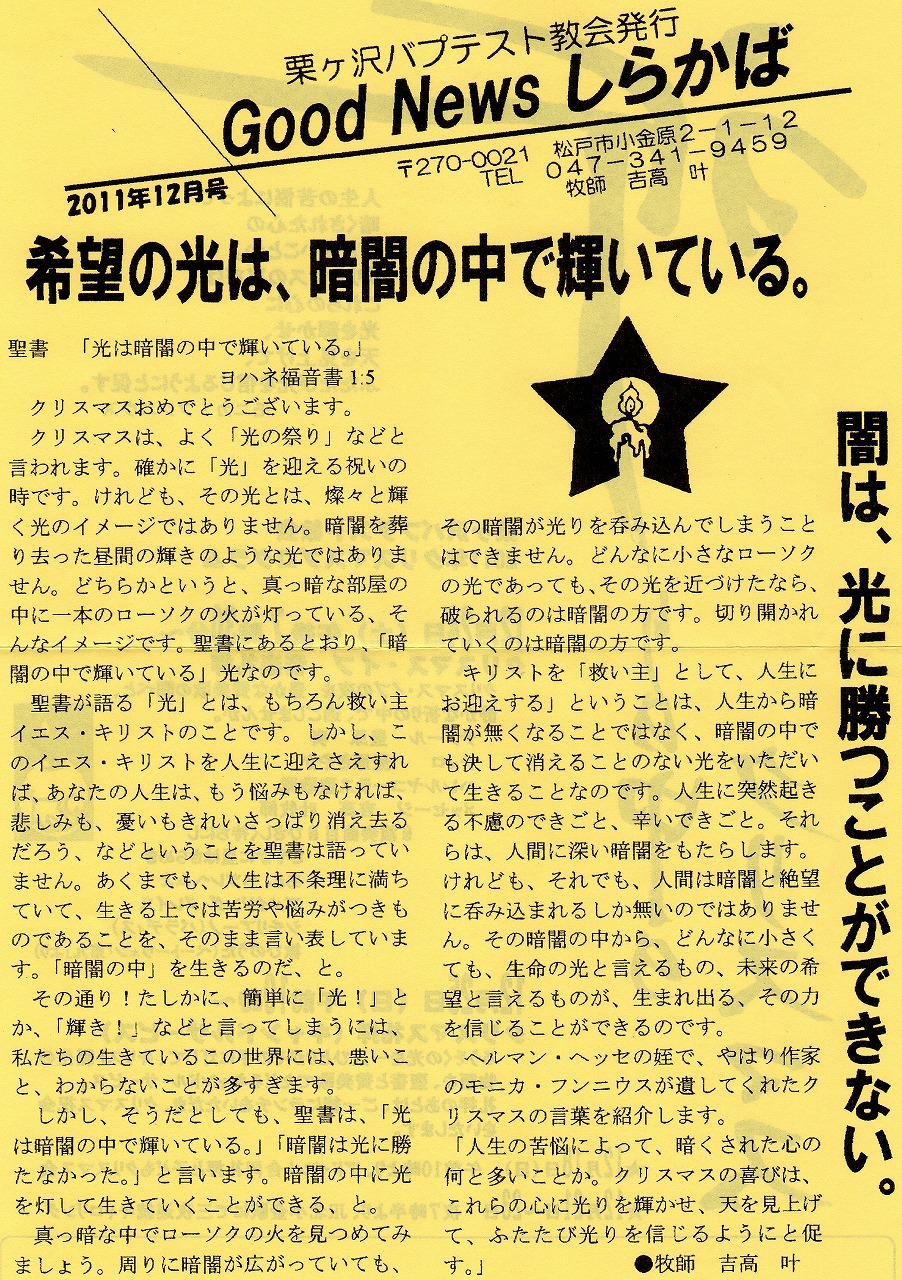【慰めの主を抱きしめて】 ルカ2:22−32
新年、明けましておめでとうございます。クリスマスに届けられた光は、暗闇を引きずる世にあって、確かに輝いています。東邦の賢者たちを、跪くべき真実の主へと導いていった標の星もまた、見上げるならば私たちの人生の夜空にあって囁いてくれます。
進んでいきましょう。救い主を見いだした者としての道を。
今朝は、ローズンゲン『日々の聖句』(栗ヶ沢教会の聖書日課)に導かれて聖書を紐解きます。生まれたばかりの赤子イエスに遭遇して安らぐシメオンの記事です。彼は、救い主を待ち続けて神殿に通う「祈る人」でした。そして、神の民の慰めのために祈り続けてきた「痛む人」でした。老いていましたが、それゆえにこそ、この祈りと業とに人生を絞り込んだ「使命の人」でした。人々の慰めのために救い主を待つ。この祈りのために礼拝を続ける。このシメオンの削ぎ落とされたたたずまいに、私たちは学びたいと思います。
その弱った腕に「慰めの徴」を抱きしめて、生きてきた全てを感謝できる。シメオンのこのような姿に、人間としての「深い憧れ」を見る想いがします。
●1月1日週報巻頭言 吉高 叶
祈りの中のクリスマス 2011.12.25
1)絆の中には傷がある
京都の清水寺で毎年暮れに発表される「今年の一字」。今年は、たくさんの人たちの予想どおり「絆」という一文字でした。東日本大震災という経験を受けて、たくさんの人たちが人間のつながり、絆の大切さを強く感じさせられた、ということに選ばれた理由があります。
この「絆」というキーワードをくり返し世論の中で用いてきたのは、ご存じ、北九州ホームレス支援機構の理事長で東八幡教会牧師の奥田知志先生です。昔から、野宿生活者やホームレスと呼ばれる人々へのケアーの活動はありましたけれども、彼は日本の中で先がけて「ホームレスの路上からの職場への復帰」「再就職・自立支援」というテーマでこの問題と向かい合ってこられました。ホームレスとは、よく考えれば、ハウスレスのことではない。住む家が無い人のことではない。むしろホームレス。家族の絆を失ってしまった人々だ。だからそのような人々に、ただ衣食住を提供するだけでは、ほんとうの意味で人生を取りもどしていくことにはならない。ホームとなる、人間の絆、人間の交わりをそこに提供し、回復しなければならない。そういって、NPOを立ち上げ東八幡教会と一体となりながら、絆の再生に力を注いでこられたわけです。
現在、内閣府の参与になられて、今回の大震災直後にも、「絆プロジェクト」を進言し、それが取り入れられて、多少、政府によって違うプロジェクトに変質してしまいましたが、「絆」というキーワードが広がる原動力になってきたキーパーソンでもあります。
先月、その奥田知志先生と、福岡の西南学院大学で講演会の仕事を一緒にしたときのことです。奥田先生は講演の中でこうおっしゃぃました。「最近、『絆』ということばがやけにはやっています。けれども、何か違うという感想をもっています。絆ということばを用いて人と向かい合おうとするなら、そこには共に生きていこうとするときに受けてしまう、痛みや傷があるものです。「きずな」という言葉には「きず」が含まれています。昨年はやったタイガーマスク現象。無名の人によって養護施設にランドセルが贈られ、それが次々と社会現象のように続いていった。そして美談として取り上げられた。しかし、裏を返せば、その匿名による援助には、『それ以上の深入りはできません』という心理が働いていると思う。つまり関わり合うことによって、こっちに傷を受けてしまうことを避けている行動でもある、ということが言えないだろうか。わたしたちの路上生活者への支援活動は、たとえばお弁当をもって近寄っていけば、目の前で、バカにするな!と投げ捨てられることがある。何週間もかかわってきて、いよいよ生活保護の手続き寸前というところで逃げられてしまうこともある。ふたたびけんかや万引きをして警察に戻ってしまう人もいる。そのたびに、こちらも傷つく。怒りがおこる。そして本人と正面切ってぶつかる。人とほんとうに絆をつくろうとすれば、それはこちらも傷を負い、痛みを味わう、でもそれでも関わっていこうという覚悟が問われるものだ。」そうおっしゃっるのです。
2)クリスマスの傷
クリスマスが引き起こされている場面を注意深く読んでいくと、神の子イエスを受けとめていくプロセスの中に、大きな痛みと傷があることを知ることができます。マリアがイエスの懐妊を受けとめていくために、同時に覚悟を決めなければならない痛みがあったことはいうまでもありません。ヨセフが、マリアとそのまま結婚することを決心したとき、ヨセフは、自分の感情との折り合いだけではなく、社会的なリスクを背負うことを覚悟しなければなりませんでした。そこには、痛みを予感し、傷を負うことへの決心がどうしても必要だったでしょう。しかし、そこで初めて生まれ始めた新しい「絆」がありました。神と人と人との三角につなげられた「絆」が動き始めたのです。この新しい絆への決心は、ヨセフの祈り、マリアの祈りを通して、受け取ることがようやくできるものとなったのです。
絆には傷がある。これは奥田さん流の「語呂合わせ」の言葉ですが、わたしは深い関係、本当の関係の中に潜む真理だと思えます。何と言っても、神が私たち人間と、父と子としての絆を結ぶために、神は深い痛みを決断され、具体的な傷を身に受けられたのです。主イエスの十字架は、まさに神の痛みの極地です。理解できない人間たちから、「お前など救い主などではない」、「おまえの神を見せてみろ」と侮辱の極みを浴びせられながら、むち打たれ、茨の冠をかぶせられ、手のひらに釘を打たれて十字架につるされ、脇腹をやりで突かれました。苦い葡萄酒を口にねじ込まれ、つばを吐きかけられました。このような痛みと傷とを自ら負いながら、神が人間に対して求めて下さっていたものは、罪赦され、贖われたものとして神の国に人間を迎えていこうとする「人間との絆」でした。神は絆のために傷を負われたのです。神のくださる「きずな」に「きず」がふくまれていました。
3)クリスマスの祈り
主イエスは、ゲッセマネの祈りで、その祈りの人生の頂点を迎えます。それはまさに、この「絆のわざ」のためには「この杯」を飲まねばならないのかという闘いでした。救いの絆のために、十字架の痛みはほんとうに必要なのですか、という問いでした。けれども、主イエスは、この絆を真実なものとして成し遂げるためには、その痛み、その傷から逃れられないことを祈りの中で受け取っていかれるのです。覚悟なさるのです。
主イエスは、しばしば、弟子たちから離れて、一人で祈ったと言われています。その祈りは何だったでしょう。おそらく、人々と関わる中で、人々と関わる中で、それらの人と共に生きるために何がもっとも必要だろうか。そしてそれらの人々との関わりによって身に受ける痛みと傷を、くり返し自分の中で想像し、それを受ける覚悟を決める、そのような祈りがなされていたのではないでしょうか。
クリスマスから始まる、神の救いのできごとには、神の痛みへの決断、ヨセフやマリアの痛みへの献身、そしてキリストご自身の苦しみへの覚悟が、祈りの中でつながっていくのです。
祈りは、誰もが知っています。祈りは、みんなが捧げます。しかし、わたしたちがクリスマスに、そして年末年始に教えられる祈りとは、このような「クリスマス」の背後にあった、「絆への祈り」のことではないでしょうか。
そして、東日本大震災という未曾有の出来事を経験した私たちが、なすべき祈りもまた、そこで捧げられていくべき祈りもまた、痛みへの共感の祈りであり、つながりや絆を結べるだろうかという不安の祈りであり、結ぼうとしたときに私たちに求められる痛みがあるとしたら、それは何だろうかという問答の祈りです。そしてわたしは、そこでわたしに担えるだけの、傷を負うことができるだろうか、悩みの祈りです。しかし祈るものは、それを問うものなのです。そして、絆づくりに心を開こうとするものにとって、大仰ではないけれどもできるだけのつながりをつくりたいと願うものにとって、何よりも必要な業こそが、祈りであります。
4)キャンドルはしるし
クリスマスには、やっぱりキャンドルサービスが似合います。昨晩は、電灯をつけた中での音楽礼拝でしたから、今日は、朝なのに暗幕まで張って、礼拝堂を暗くして、一人ひとりがキャンドルを手にして燭火礼拝を捧げています。これは、何もクリスマスらしい雰囲気を味わいたいからではありません。人の顔がよく見えるために、文字がはっきりと読めるためにローソクの火を持つのでもありません。それならば、はじめから電灯をつけた方がいいのです。そうではなく、このキャンドルは、私たち一人ひとりが、イエスさまという存在をこの身に受けとめようとしていることの「しるし」だからです。そして、わたしという存在の意味性も、このキャンドルの光から学ぶための「しるし」だからです。
キャンドルの光は、飼い葉桶に生まれたイエス・キリストの「しるし」です。もっと暗ければはっきりわかると思いますが、薄暗い中でも、キャンドルの炎が周囲の闇の方に光を放射しているのがわかるでしょう。
イエス・キリストがこの世に来られ、寝かされた場所は、暗く貧しい飼い葉桶でしたが、その小さな低みの極みである飼い葉桶から放射した光は、「柔和」「優しさ」そして「希望」の光でした。でもそれこそが、いま、世界がほんとうに必要としている力ではないでしょうか。「柔和」は、あらゆる憎しみと暴力への答えとして。「優しさ」は、人間が思いやりや共感する心や慈愛を失いつつあることへの答えとして。「希望」は、孤独のまま捨て置かれる人や、人生への意味を見いだせない人たちへの答えとして。その光は、大きなひかりではありません。それを手にした人に届く光です。照らされているのは、わたしなのです。クリスマスの光は、何を隠そう、このわたしへのコンタクトなのです。
5)キャンドルには芯がある
ちいさなキャンドルです。それでも、これが光である以上、暗闇に対しては決定的に勝利しています。どんなに小さな光でも、暗闇がそれを呑み込むことはできず、むしろキャンドルの光を動かせば、切り裂かれていくのは闇の方です。一挙に全体を明るくするような光ではなく、(人間はそれにあこがれますが、そういう光ではないところが意味深い)光がわたしにコンタクトし、そのわたしがこの光を持ち運ぶところが照らされていく。そういう光を手にして生きる、それが、人が信仰をもって生きていく実際的な姿を現しているのではないでしょうか。キャンドルを見てください。一人ひとりのキャンドルには「芯」があります。このキャンドルの炎には「芯」がある。でも、礼拝時間も進みましたから、その芯がずいぶん短くなりましたね。わたしは、この芯にキリストが重なります。自らの命を捧げ、削り、身を溶かしながら、全ての人々に、生きるに必要な信仰と望みと愛の力を放射した、主イエスの生涯。それが新しい命の光の「芯」です。
私たちも、しばしば愛を語ります。しばしば平和を語ります。そして希望を口にします。でも、その愛に「芯」はあるか、と問われたら、わたしたち自身が、光の芯ではとうていありえません。わたしたちではない。わたしたちの何かの力が、平和の芯なのではないのです。それらの「芯」は、イエス・キリスト。私たちは、私たちの内に、「芯」を迎え入れ、私が溶かされ用いられながら、真の光の放射へと奉仕することを、求めていきたいと思います。
この小さな芯は、時を経て燃え尽きます。主イエスもそうでした。しかし、主イエスは、そのすべての祈りと痛みと傷とを受け、ご自身を燃やし、ご自身を溶かし、与え捧げられたのち、三日後に復活をなさいます。そして、もはや消え去ることのない、信仰と希望と愛の芯となられて、信じるわたしたちの永遠の光の源となられました。
クリスマスと十字架と復活。イエス・キリストは、光であるために生まれ、光であるために傷つき、光となって永遠を生きておられます。
6)祈りは光のわざ
小さくて良い。でもこのキャンドルの光のように生きる。光を受け、光を返して生きる。そのための道は、祈りにあります。ヨセフが、マリアが、主イエスが、祈りを通して光を灯し続けたように、わたしたちも祈りの中で、人々の悲しみをわかろうとし、それを突き破る喜びを願おうとし、もし自分にできることならば、と(祈りの中で)求めさせられていくのです。人が、繋がろうとするとき、イエス・キリストの傷の絆に支えられるのです。その絆は、日々の祈りによって確かにされるのです。
この祈りが、祈り続けるわたしが、きっと、わたしを必要としてくださる誰かとの絆へとわたしを導いてくれるでしょう。
随想・クリスマスイブ
小学生のとき、クリスマス・イブが怖かった。終業式が必ず12月24日で、通知表を渡される日だったから。1〜5までの数字が並んでいる欄もぞっとするが宿題をしていかなかった回数、ふざけて廊下に立たされた回数なども書かれていて、そちらの方がずっとヤバかった。
けれど、クリスマス・イブは、ほんとうは大好きだった。イブ礼拝が終わると、みんなでキャロリングに出かけた。日赤病院の中庭で讃美歌を歌うと、真っ暗だった病棟の窓に次々と電灯が灯り、中から患者のみなさんが顔を出して聞いてくださった。最後にメリー・クリスマス!と叫ぶと、一斉にメリー・クリスマス!!という声が病院の中庭に響いた。とてもいい気持ちだった。それから信者さん宅を転々とし、歌っては上がり込んでお茶菓子をいただき、また次の家へと歌って廻った。終点は小森家(代表役員)と決まっていて、そこではおにぎりや豚汁が出た。小森を出る頃には、夜中の12時をとうに過ぎていた。そんなことが許されるイブが好きだったし、温かかった。
そして、夜中に帰宅したぼくを、毎年待っていたのは、通知表を手にして、冷気を漂わせる母親だった。
●12月18日週報巻頭言 吉高 叶
お言葉どおり、なりますように
ルカ福音書1:26−38
1)二つは一つ
フランスの有名な美術館には、二枚の絵が縦に並べられています。その上の方の絵は、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱いて、ふくよかな笑顔を見せている母親の絵です。まさに、母親としての至福の時を得ているかのようです。下の方の絵は、兵士の制止を振り切ってわが息子が張り付けられた十字架にすがりついて泣いている母親の絵です。その顔は苦痛と悲しみにゆがみ、母親として受けなければならない最大の悲劇が描かれています。
この二枚の女性は、一人の女性です。御子イエス・キリストの母として、神のみこころの生命を体に受け、また神のみこころ故に、母としてイエスの死を身に彫り込まれることになってしまったマリアの、対称的でありながら一つの共通のメッセージを表現した絵ではないかと思います。
キリストの母とされていったマリアの人生は、「クリスマス物語の美しい脇役」という点だけでは理解することが不可能です。受胎告知、マリアにとって、「母となる喜び」というモチーフではなく、キリストを迎え入れるとまどいと苦しみ、キリストに刺し貫かれる痛みと、しかし、そこにこそ注がれている神の祝福という深いモチーフを持っていると言えます。
2)恵まれた女?
「恵まれた女よおめでとう」。突然、何の脈絡もなく御使いの知らせがマリアを直撃します。大きな衝撃がマリアを襲います。「あなたは身ごもっています。その胎内の子は神の子です。おめでとう。」というのです。
冗談ではありません。そんなものが「恵み」でしょうか。言葉でいくら「恵まれた女」と言われても、「それは恵みだ」と連呼されたとしても、それは恵みなんぞではありません。どう考えても迷惑ですし、じっくり考えれば考えるほど理解できないのです。
「自分が願っていたことが叶えられる」とか、「自分が待ちこがれていたことが実現する」、それならすぐにでも恵みだと理解できましょう。けれども、期待もしない、予想だにしない、しかも困ったことになる。どうしてそれが「恵み」でありましょうか。
事実、この「恵み」によって困ったことになりました。マリヤは、身持ちの悪い女だと陰口をたたかれて生きなければなりませんでした。子どもを出産するときにだって、彼女は屋根の下で出産することを拒絶されました。(泊まる場所がなかった、の「場所」とはトポス・居場所のこと)、どこにもいさせてもらえなかったのです。拒絶されました。人間を出産する場所とはとうていない思えない家畜小屋で産むしかなかったのでした。マタイ福音書によれば、出産後ただちに彼女は、この赤ちゃんを連れてエジプトに逃亡生活をしなければならなくなります。そしてやがてナザレにもどってからも差別は激しく、ヨセフは石切の仕事、羊飼いと共に最も低下層の人々にあてがわれた仕事をして生きていきました。やがて、わが子が30歳を迎えた頃、当の本人が「時が来た」といって母の元を離れ宣教活動に旅立っていく。挙げ句の果てに、ユダヤの指導部から指名手配書が廻るようになり、そして逮捕され、エルサレムで犯罪人の一人として息子が処刑されていくのです。「恵まれた女よおめでとう」と呼びかけられて始まった彼女の人生ですが、マリアにとってそれは、まさに身を差し貫かれた人生ではありませんか。
いったい「恵み」とは何なのでしょうか? 思いがけなく嬉しいことがあった時、「今日は恵みをいただきまして」と私たちは口にします。それは嬉しい故に「恵み」と言い表すことが最もふさわしい、そういう実感からきます。しかし、私たちがそのような嬉しい実感を伴って語っている「恵み」というものと、マリアが受けなければならなかった「恵み」とはどうしても同じものだとは思えないのです。
3)お言葉どおりに
マリヤにとってそれは不可解なままでした。ガブリエルは言います。「あなたは神から恵みをいただいた」と。「その子は偉大な人になる」と。「神にはなんでもできないことはない」と。凄い言葉の連続です。しかし、その言葉はそのまま即、マリアにとって「幸せになれる」という確証の言葉ではありません。「イエスが大いなるものである」ということは、実際には、マリアが出世した息子の晴れ舞台を見ることができた嬉しい母だったということとはほど遠いものでした。息子イエスが、「ほんとうにこの人は神の子だった」と告白されるのは、まさに十字架の場面においてだったからです(百卒長のことば)。
「神には何でも出来ないことはない」という確かに天使は言いました。だからといってマリアにとって実際には「何でも欲しいものが手に入る」という意味ではなかったのです。「神にはできないことはない」ということは、まさに、人間の罪の赦しを、神が御手に引き受けて、神の子が人間の身代わりになって十字架で苦しむようなことさえ神にはおできになる、という意味をもった言葉でした。しかし、そのような「神のみこころ」が、この時のマリアにわかったはずはないのです。
ですから、マリアは、「恵み」といわれても不可解なままでした。「恵まれた女」と呼びかけられても、何がどう恵まれるのかは分からないのです。いいえ、直感としては、「結婚前に身ごもる、これはたいへんなことだ。処罰されてしまう。」「ヨセフを巻き込んで、人生が狂ってしまう。」。それは、すぐにわかりましたから、もうとにかく、後でどんなに恵まれるのか知らないけれど、その子が大いなるものになるかならないか知らないけれど、とにかく「嫌です」「お願いです、やめてください」という気持ち以外持ちようがなかったはずです。
しかし、どんなに不可解でも、どんなに抵抗しても、どんなに「これは嬉しい知らせだ」という実感を持てなくても、もはや神さまのなさることなのです。恐ろしいまでの衝撃を受けながら、そのような中で、人間として神の前に立たされた時に、人間にかろうじて語り得る言葉があるとするならば(そしてこの言葉を人間はなかなか簡単には言うことができないのですが)、その言葉こそが、
「わたしは主のはしためです。お言葉どうりこの身になりますように」
なのではないでしょうか。もちろん、この言葉は納得の言葉ではありません。よく言われる「謙遜の姿」でもありません。
人間というものは、神のみこころの前に、不可解なまま立つしかない、なんと力無きものでしょうか。そして、神のみこころとは、なんと、人間を揺さぶり、人生を差し貫き、苦しみを与えながら、与えられるなのでしょうか。その、「神の大いなる恵みの業」を前にして、人間は、ただ不可解なまま立ちすくむしかないし、そこで、「私は主のはしためです」としか言いようのない、なんと限界を知らされてしまうものなのでしょうか。
4)母と子のつながり/ みこころのままに
「お言葉どおり、この身になりますように」。
拒絶の中で、この言葉と同様の言葉を語られた方がいますね。このマリアの子である主イエスが、ゲッセマネで祈られたときの言葉です。
「父よ、御心なら、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの願いではなく、御心のままに行ってください」(ルカ22:42)。
神の御心と人間、神の救いと人間。そこには人間の嬉しい実感とか喜びの実感で捉えようとしても、どうしてもできない「断絶」があるように思います。言い換えるなら「神の恵み」と「人間の恵み」の間の断絶です。
神の救いの恵みは、主イエスにとって、この世にあっての最大の苦痛を背負うというかたちでしか成し遂げられませんでした。母マリアと主イエスは、共に、神の大いなる恵みの業のもとで刺し貫かれてしまう苦しみを背負わされました。そして二人とも、この言葉を語ります。「お言葉が、御心がなりますように」。
「神の恵みの業」の前で、人間が結ぶしかない言葉こそ、「わたしはあなたのしもべです。お言葉が、御心がなりますように」という言葉です。
5)不可解さの恵み
しかし、今、わたしたち人間は、神の恵みというものが不可解でしかない、ということに一つの希望を与えられるのかもしれません。自分の嬉しい実感の問題として恵みを捉えようとすれば、「恵み」は不可解であっては意味がないのです。けれども、視点を移してみたいのです。
東日本大震災で犠牲となった子どもたちは650人を超えます。何を失った人たちよりも、この子どもたちの親たち、とりわけ母親の苦しみはいかばかりでしょうか。どんな慰めの言葉も癒せないでしょう。母親たちには「なんでや」という悲痛な叫びしかないはずです。時間が経ったとしても、あるいは「みんなも被災したんだから」と考えようとしても、ご遺族にとって、「どうして」という怒りと悲しみは、いつまでも込み上げてくるのではないでしょうか。人間が、どんなに意味づけようとしても、また納得しようとしても、のみこめない、癒されない「不条理と不可解」とがそこにはあります。つまり、人間には、もはやどのような言葉をもってしても、あの母親たちにあの遺族に「恵みです」と語れる力はない、ということです。
人間の世界に、「喜び」はたくさんあります。人間が生み出すものの中にも「恵みです」と祝えるものはいくらでもあります。しかし、どうしても、そして誰一人として、もはやそのような時、そのような場では、「それは恵みです」と語れることが、決してできないような場面があるし、そういう時があると思います。そこに、「人間というものが、究極的には救いをもたらすことができないのだ」というどうにもならない限界線があるのではないでしょうか。
しかし、(このことは、気安く言おうとは思いません。神にすがりつくような気持ちで言うのですが)人間にとって不可解で理不尽でどうにも理解できない、いいえ、引き裂かれるような苦しみしか見えないようなただ中で、「神の恵みはあなたの人生を扱っている」「神の恵みはあなたを包んでいるのです」と言うことができる存在があるとするならば、それが神さまなのです。苦しみもがく人間の現実も、神さまの救いの捉えきれない御業の中で「ある」。それだけではなく、実は、神ご自身が、キリストご自身が、自らもその苦しみ、痛みを身に受けながら、救いを打ち立てようとされている。そのことに目を向けさせられる一点において、私は、神の恵みが不可解であることの中に、真実の救いというものがある。そのことをマリヤの受胎告知は聞かせようとしてくれているのではないかと思うのです。
身もよじれるような母たちの涙と叫びに対して、誰も「恵まれた女よ」と呼びかけられはしない。ただ、そこにキリストが生まれ、そこでキリストがその女たちの胎をひらいて生きるものとなり(そう!生まれ得ぬところから命を宿し)、そしてその苦しみを背負い、しかも、全ての人々の罪と苦悩とを赦す御業を、今も成し遂げようとされている。そして、神は、その死んでいった子どもたちと、苦しめる母たちとを、キリストと共によみがえらせ、神の正しさの完成のいのちとして再び起こしてくださるという、この神さま、「生と死」の主としてのる救いの御業からのみ、そこからのみ、彼女たちに「恵まれた女よ、おめでとう」という言葉は発せられるのではないかと思うのです。
6)二つは一つ
フランスの有名な美術館には、二枚の絵が縦に並べられています。上の方の絵は、母に抱かれ、静かに眠る赤ん坊の絵です。もっとも小さい姿でありながら、最も幸せな表情を見せています。下の方の絵は、人々が指さしてあざけり笑う中を、十字架に張り付けられながらも天を見あげて祈っている方の絵です。額から、掌から、そして脇腹から血を流し、痛みに身体をよじらせながら、神に向かって人々の赦しを叫ぶあの方の絵です。
このあまりにも激しく違う二枚の絵は、しかし、一人の救い主の人生の意味を共に描いています。その証するメッセージは一つなのです。クリスマスはすでに受難を含み、受難はクリスマスから始まるのです。人々の罪のために苦しむ、この神のみこころを託されて生まれた赤ん坊こそがキリスト・イエスです。ガブリエルは、神が人間の罪のために苦しむ決断をなさったことを携えて一人の女のところに来たのです。そこに人間の理解を超えた神の恵みがありました。
神にはできないことはありません。神だけが、誰も慰めることの出来ない人間の苦しみの場に立つことがおできになります。神だけが、人間が言葉を失う場所で、赦しと救いの言葉を放つことがおできになります。神だけが、馬小屋で生まれることがおできになり、十字架で死ぬことができます。イエス様の人生は、人間の人生の喜びをかけ離れています。だからこそ、イエス・キリストしか、放つことの出来ない光があったのです。
「神には何でもできないことはありません」。
「私は主のはしためです。お言葉どおりこの身になりますように」
了