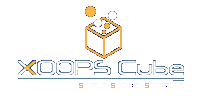
説教全文・和解のつとめにつかえる(平和祈念礼拝)
投稿日時 2012-08-13 21:43:32 | カテゴリ: メッセージ
|
和解のつとめにつかえる
Ⅱコリント5:17−21
1)和解できないものの頂点
67回目の原爆記念日を、8月6日と9日に迎えた。そして、67回目の敗戦記念日を今週15日に迎えようとしている。今年も、ヒロシマとナガサキの原爆死没者名簿に9000人を越す死没者名簿が加えられた。この方々は、実に、67年間、被爆の後遺症に向かい合い、それを引きずりながら生きてこられた苦しみの証人たちであった。
もう10年も前のことになるが、長崎教会の中高生のキャンプの講師として長崎県の山の中にあるキャンプ場で過ごしたことがある。美しい渓谷の傍らにある語らいの広場で、夜遅くまでリーダーたちと語らっている間にブヨに噛まれ、ふくらはぎが腫れあがった。キャンプを終え、長崎市内の皮膚科の病院に治療にいったときのこと。待合室でほんの15分ほど待つ間にも、受付で「原爆です」といって「原爆手帳」を持って治療に来る70歳前後の患者が二人もあった。あぁ、原爆の後遺症、それはケロイドなのか何なのか、そのような負の遺産を身体に刻まれて、いまも治療を続けている方々が、ほんとうにこのようにいらっしゃるのだ、ということを感じた体験だった。こうした人々にとって、たとえ戦争が50年以上も昔の過去の出来事であったとしても、やはり戦争はいまの痛みとして、いまの呪いのように、終わっていないのだと思う。身体に残された傷跡ばかりではないだろう。たくさんの人々の心の中に、それは刻まれているのだと思う。
瞬時にしてヒロシマで14万人、長崎で7万人の命を奪った原子爆弾。しかし、その一発ずつの爆弾が放った熱や放射能の影響によって、さらには23万人の苦しみと人生の闘いが積み上げられてきた。
原子爆弾を開発した人々は、その衝撃波の武器としての凄さに目を見はったというが、原子爆弾の持つ50年も60年も続くことになる、悪魔的な影響力については、想像だにしていなかったのだ。制御できず、想定できないものを生み出してしまった。あまりにもやっかいなものを生み出してしまった。そのような核兵器が、いまだに廃絶されることなく、あたかも核保有国であることが、抑止力を身につけた強い国の象徴であるかのようにして、今もなお保有を画策する国が拡散しているという現実に、頭を抱え込んでしまうし、それが恐ろしくてならない。
私たちの肉体はやわらかい。だから、ひとたび鉄の弾丸がこの肉体に撃ち込まれ、鉄の破片がこの肉体に突き刺さり、また火炎のかたまりにこの肉体が焼かれるならば、たちどころに私たちは、絶命する。生きてはいられない。そうだ、武器というものと私たち人間とは、武器というものと私たち生命体とは、共存できなければ、和解もできないのだ。
私たちは、誰とでも共に生きることができるかもしれないという可能性に開かれている。そして、さまざまな違いを超え、禍根を超えて、どんな人とも和解できるという希望を持って生きていたいと願う。しかし、この生命の肉体を貫く武器とは、私たちがロボットでないかぎり、本質的に共存、和解ができないのだ。そして、原子爆弾は、人間が生きるために決して和解できないものの頂点に位置するものだと言える。
私たち日本に生きる者が、8月が来るたびに原爆が投下された日を忘れないことの意味は、人類にとって普遍的な役割を担っている。それは、生命あるものが、決して和解できない最たるもの、にもかかわらず、一度はこの世界が浴びてしまったもの、この原子爆弾を、まさに和解不可能なものとして指し示し続けることにある。一昨年、秋葉前広島市長が、平和宣言の中で語られた言葉「原爆は廃絶されることのみに意味がある」という逆説的な真実こそが、まさに生命世界の基本線にならなければならないのだ。そう、人間が、生命が、なぜ、決して和解できないものを保有し、「廃絶されることのみに意味があるもの」を温存しようとするのか。人間の精神は、人間の倫理観はいったいどうなってしまったのか、それらは、生命世界を守るために役立たないのか、という根本的な問いを、問いかけ続けなければならないのである。
この和解できないものを、これほどに和解できないことがわかっているものを、「和解できないものと」はっきり定めていく。このことは、和解のために祈り、働こうとする者たちの基本姿勢でなければならないだろうと思う。
2)和解のつとめに
人間にとって、歴史にとって、あまりにも決定的な影響を残した出来事、しかもそれは人間の人間性を疑わしめるような出来事を経験した後の時代のことを<ポスト○○>と表現してきた。ポスト・アウシュビッツ、ポスト・ヒロシマ、ナガサキ、ポスト・チェルノブイリなどである。その経験から何を学び、何を改め、方向転換ができたのか、という人類の姿勢を問う思想の建て方である。
ドイツの哲学者、テオドール・アドルノは「アウシュビッツ以後、詩を書くことは野蛮である」と語った。あれほどの残酷と悪魔性を、人間が秘めていることが明らかになったからには、あまりにも情緒的に、楽天的に、愛を語り、人間の幸福を詩に書くことは、もはや人間にはできないはずだ。もしそれができるとしたならば、あのアウシュビッツの事実をあたかもなかったかのように考えることのできる、野蛮な魂である。そのように訴えているのだと思う。そして、文化や芸術が、どのような地平でなされるべきであるかを問いかけているのだと思う。
私たち人類は、ポスト○○と語られるような経験を更に繰り返してきている。なぜ、あれほどの経験をしながら、また繰り返すのか。アドルノが語るように、人間の本質は、それほどまでに野蛮なのか。果たして、神は、人間を野蛮なものとしてお造りになったのか。ということは、それほどまでに、神ご自身が野蛮なのか・・・。
否! 神はこの世界を美しい調和のうちに創られた。その調和を保つように、調和を維持するようにと人間を祝福した。それを忘れ、調和を乱し、欲望と暴力の中に生きた人間に、さらに神は、一人子イエス・キリストを贈り、ご自身との調和を取り戻そうとし、また和解するつとめを人間に示し、授け、招いた。神ご自身が、決して野蛮ではなく柔和であり、怒りではなく赦しであり、憎しみではなく愛であることを、キリストによって神ご自身が現された。ポスト・キリスト。キリストをいただいた後を生きる人間は、まさに和解を受け、和解のために生きるものと招かれている。これが、歴史における決定的な分水嶺であるはずだ。キリストの和解の業を、歴史の分かれ目と捉える生き方こそが、神の御心を生きるというキリスト者の生き方である。
人間は野蛮なのか。つまり神そのものが野蛮なのか。そのような問いが、この歴史の中で繰り返されるほど、人間はたしかに罪深い。しかし、神の性質は、明確に示されている。それは、調和であり、それは共存であり、それは和解である。人は、和解のつとめに仕えるために生まれ、和解のつとめに生きるためにキリストに結ばれたのだ。
人の幸福は、さまざまな形で追求される。時に、人は誰かの犠牲の上に、幸福を築くことがあり、また自分の幸福のために、誰かを倒そうとすることがある。しかし、そのような幸福を神に求めるとき、私たちの祈りの先に、ほんとうに神はいるのだろうか。
個人的な幸福を求めてはならないというのではない。いな、私たちは、自分の幸福を犠牲にして神を信じなければならないというのではない。ただし、私が幸せでありたいと願う、その傍らにいる隣人が幸せであることを祈り、私たちが豊かであることのために、あなたがたもまた豊かであるような、そのような祈りを忘れないことが、調和と和解を御心とする神の前での人間の慎みであろう。
人と人、国と国、民族と民族、文明と文明が、こんにち、なかなか折り合いをつけられず、その引き裂かれた間柄の中に、さらには、核兵器や生物兵器を持ち込もうとしている20世紀から21世紀に持ち越された、悲劇的な文脈の中で、私たちは個人的な幸せをもたらすものだけを福音を呼んではならないのだ。むしろ、和解という御心と、和解のつとめという作用のことをこそ、福音の本質として心に刻み、2000年を生きてきた、どの時代のキリスト者以上に、和解の福音につかえる責任を背負わねばならないのだと思う。
私たち日本社会を生きる者に、新たに、ポスト・東日本大震災、ポスト・フクシマというテーマが加えられた。人間を苦しめ、調和を崩壊させ、社会を共につくれなくしてしまおうとする力は、人間の忘却や、見放しや、利己心を餌にして、放っておけばどんどん膨れあがってしまうのではないだろうか。私たちは、そこでもまた、和解のつとめをおぼえる者として作用することが求められている。そのためにも、忘れないこと、自分のこととして痛むこと、祈り続けることから離れてはならないのである。また、和解できないものを峻別し、和解を妨げるものを退けるまなざしと、勇気を持たねばならないのである。
3)歌をください
豊原奏さんに「歌をください」を歌っていただく。
中田喜直さんが書かれた「歌をください」。この求めなければならない「歌」こそが、キリスト者にとっては祈りであり、そうでない者にとっては想いであろうと思う。哀しみを勇気に変える歌、苦しみを慰めに変える歌、憎しみを祈りに変える歌、あやまちを恵みに変える歌。わたしたちが、それをいただくことによって、負の遺産を、希望に転じていくことができるような、そのような転換の力を、私たちはいま、求めようではないか。
一人一人が、この歴史、この時代の中に生きることを位置づけられ、かけがえのない人生を生きている。その人生を大切に歩み、次の時代に生まれてくる命たちのために、「それでも人間はこのような祈りとこのような歌で生きてきたのだ」という希望の手がかりを譲り渡そうではないか。私たちが、それぞれの人生を終えて、神のもとに帰されるとき、私たちは、「主よ、あなたの和解の御業のために私なりに精一杯生きてみました」と、神に告げ得るものとして、生きていこうではないか。
了
|
|